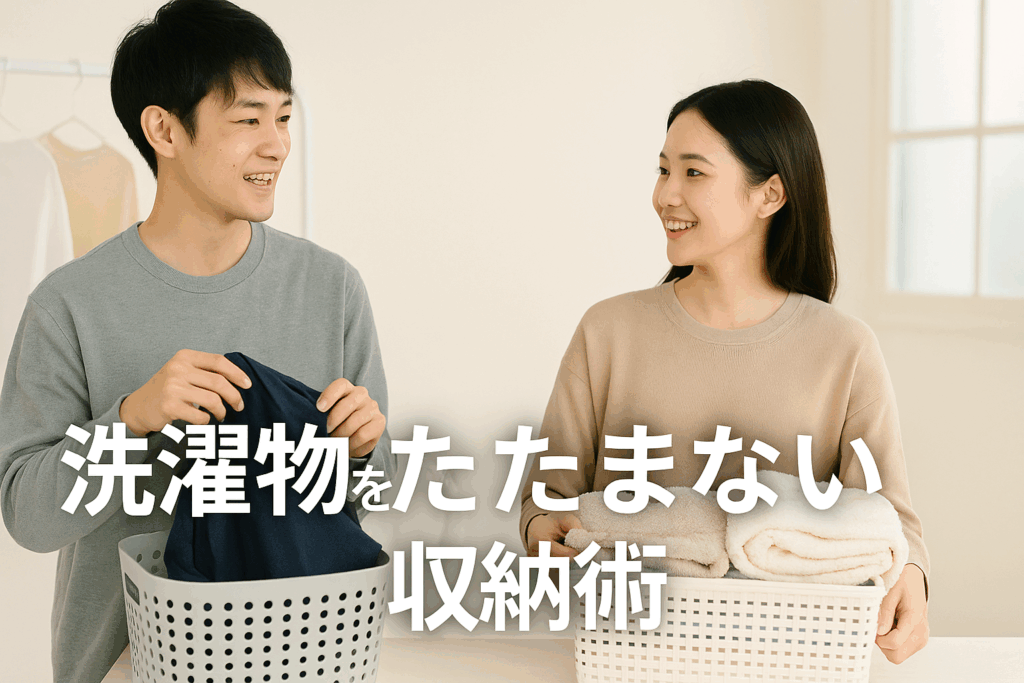
はじめに
「洗濯物をたたむのが面倒…」。
その悩み、実は多くの人が毎日つまずいている家事ストレスです。
この記事では、ズボラでも“自然に片付く仕組み”を作る方法を、今日から実践できる形で紹介します。
この繰り返しを止める最も簡単な方法が、**“たたまない収納”**です。
必要なのは、根気よりも「動作を減らす仕組み」。
掛ける・入れるを中心にするだけで、洗濯後のストレスは想像以上に軽くなります。
なぜ「たたまない」とラクになるのか
洗濯物をたたむ工程は、広げる・折る・運ぶなどの動作が多く、時間がかかります。
この手間を「干す段階でハンガーに掛ける」「乾いたらそのまま移す」「入れるだけのボックスを使う」に置き換えれば、家事の動線が一気に短くなります。
“丁寧にたたむこと”よりも、“続けられる仕組み”を優先する。
これが、散らかりを連鎖させないコツです。
さらに、心理的にも「たたまなきゃ」と思う負担が減るため、気持ちの面でもラクになります。
家事は“完璧”より“継続”。
毎日少しでも気がラクになる仕組みを整えることこそ、長続きのコツなのです。
基本ルールは3つ

- 干す段階からハンガー運用に切り替える
- 畳まずに入れられるボックスを常設する
- しまう場所を干す場所の近くに寄せる
この3つができれば、十分に整います。
特に「近さ」は重要。ランドリースペース近くに収納を置くだけで、移動が減り片付けやすくなります。
たとえば、洗濯機の上に伸縮式のハンガーバーを設置し、乾燥が終わった衣類をそのまま掛けるだけで家事動線は劇的に短縮されます。
また、家族ごとにボックスを分けておけば「誰の服か探す時間」もなくなり、自然と整理整頓が続くようになります。
ハンガー収納を“干すところ”から始める
シャツやブラウスは干す段階でハンガーに掛けましょう。
乾いたらそのままクローゼットへ移動。
「たたむ→運ぶ→掛ける」が「掛ける→移す」に短縮されます。
クローゼットに余裕がない場合は、突っ張り棒やポールハンガーを使って“受け取りレール”を作ると便利です。
同じ形のハンガーを使うと見た目も整い、滑りにくく扱いやすくなります。
さらに、ハンガー収納を快適に続けるためには、**衣類の「掛ける基準」**を決めておくのもポイントです。
たとえば「シワになりやすい服は必ず掛ける」「Tシャツ類は週末まとめて掛け直す」といったルールを自分なりに設定しておくと、迷わず片付けができます。
また、乾燥機を使用する家庭では、**“乾燥→そのまま掛けるスペース”**を確保しておくと理想的です。
ハンガーラックを洗濯機の横に置くだけでも、取り出してすぐ掛けられるため、家事時間をさらに短縮できます。
日々の動作を1つ減らすだけで、気持ちにも余裕が生まれます。
たたまない収納は、“ズボラの知恵”ではなく、“暮らしの最適化”。
片付けが苦手な人こそ、積極的に取り入れる価値があります。
「投げ入れるだけ」のボックスを活用

タオルや部屋着、靴下などは“投げ入れ収納”でOKです。
深めのボックスを使って、種類ごとまたは人ごとに分けて入れるだけ。
Tシャツ類はひとつのボックスへ、下着や靴下は家族ごとに分け、パジャマは寝室の入り口に置きます。
「どこに入れるか」だけ決めておけば、たたまずに片付くのにスッキリ見えます。
ズボラでも続く最大のポイントです。
さらに、この方法を長く続けるコツは「見た目よりも動線を優先する」こと。
ボックスのデザインより、取り出しやすさと戻しやすさを重視しましょう。
中身が見えるタイプなら、どの箱に何が入っているかが一目でわかります。
もし来客時に隠したい場合は、ふた付きの布ボックスを使えば簡単に“見せない収納”へ早変わりします。
また、ボックスを積み重ねるよりも横並びに配置すると、取り出す動作がスムーズになります。
たとえば洗面所やランドリーラックの下段に、家族全員のボックスを並べておくと、朝の身支度が効率的になります。
「使ったら戻す」が自然にできる環境を整えるのが、散らからない秘訣です。
家族別ゾーンで“自己完結”を促す
家族が多いほど洗濯物は増えます。
各自の収納ボックスを設け、乾いた洗濯物をそこに“投げ入れるだけ”。
「自分の服は自分で片付ける」ルールを作れば、家族の協力も得やすくなります。
子ども用には、自分専用のカゴを用意すると“遊び感覚”で片付け習慣が身に付きます。
子どもが小さいうちは、カゴの色やイラストで“誰のものか”を区別できるようにしておくと便利です。
年齢が上がったら、自分で畳む・掛けるを選べるようにしてあげると、自然と責任感が育ちます。
また、家族ゾーンを作る際は、家族動線の交差を減らすこともポイントです。
たとえば、寝室近くにボックスを置くことで、リビングに洗濯物があふれるのを防げます。
少しの配置換えで、暮らし全体が驚くほどスムーズになります。
子どもの整理整頓を教えるヒントは、部屋が片付けられない子供のための簡単整理術6選にも詳しく紹介されています。
干す場所としまう場所を近くに

たたまない収納の成功の鍵は、動線の短さ。
干す場所と収納場所をできるだけ近くに置くだけで、片付けの手間は激減します。
ベランダやランドリールームのそばに小さな棚を置きましょう。
スペースがない場合は、壁掛けラックや吊り下げ収納を活用。
「動かさずに片付ける」が最大の時短術です。
さらに、乾いた衣類を一時的に置ける“仮置きスペース”を作っておくと便利です。
たとえば、洗濯機横のカウンターやラック上段を使えば、片手でサッと掛けたり入れたりできます。
日々の小さな動作を減らすことが、結果的に“片付けの習慣化”につながります。
洗濯トラブルを防ぐ豆知識
洗濯ネットの扱いを間違えると、衣類の劣化や絡まりの原因になります。
ドラム式を使っている方は洗濯ネットがなぜドラム式に不可?使用前に知っておくべきことをチェックしておきましょう。
また、夜に干す場合の注意点は夜洗濯物は危険!ゴキブリから守る4つの対策とはを読むと安心です。
さらに、洗濯トラブルを避けるためには“洗濯機まかせ”にしすぎない意識も大切です。
洗剤を多く入れすぎると繊維に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。
洗濯槽の汚れも見逃しがちですが、月に一度は槽洗浄モードやクエン酸でお手入れを行いましょう。
また、洗濯ネットのサイズを衣類に合わせることも重要です。
ネットが大きすぎると摩擦が起きやすく、逆に小さすぎると洗いムラが発生します。
“ちょうどよいサイズ感”を意識するだけで、衣類の寿命はぐっと伸びます。
洗濯物を入れる順番も意外と見落とされがちです。
先に洗剤を入れてから水をため、しっかり溶かしてから衣類を入れると、洗いムラや洗剤残りを防げます。
日々のちょっとした習慣が、結果的に衣類を長持ちさせる秘訣になります。
また、柔軟剤を使うときは、**“入れすぎないこと”**がポイントです。
香りを強くしたいからと多く入れると、繊維がコーティングされ吸水性が下がり、タオルの使い心地が悪くなります。
適量を守ることで、洗濯物がふんわり乾きやすくなり、結果的に時短にもつながります。
家事全体をラクにする導線設計
洗濯導線を見直すと、家事全体の効率も上がります。
時間を決めて回す仕組みづくりには家事を減らすコツで1日30分自由時間を作る方法が役立ちます。
また、素材別の扱い方を知りたい人は毛玉知らずの衣服へ:素材選びから洗濯術まで徹底ガイドもおすすめです。
さらに、家事全体の動線を考えるときは「一筆書きのルート」を意識すると効率的です。
たとえば、朝の支度からゴミ出し、洗濯、朝食準備までを時計回りの流れでこなせるように配置を工夫します。
洗濯機から干し場、クローゼットへの距離を短くするだけで、移動時間が減り、1日の家事負担が大きく変わります。
また、干す・たたむ・しまうを一か所で完結できる“ミニ家事ゾーン”を作るのもおすすめです。
洗濯機横にハンガーバーと収納ボックスを設ければ、服の移動が最小限になります。
小さな工夫ですが、「戻すのが面倒」という心理的ハードルを下げてくれるため、自然に片付けが続くようになります。
まとめ
「洗濯物をたたまない収納術」は、ズボラだからこそ続けられる新しい暮らしの形です。
ハンガーで干して掛ける。ボックスに入れる。干す場所のそばで完結させる。
この3つの仕組みで、部屋も気分も整います。
さらに、家族で共有できる仕組みを作れば、洗濯のストレスは確実に減ります。
暮らしをよりシンプルに整えたい人はモノを減らして暮らしが変わる|3つの視点から学ぶシンプル生活の始め方もあわせて読んでみてください。
あわせて読みたい関連記事
・部屋が片付けられない子供のための簡単整理術6選
・モノを減らして暮らしが変わる|3つの視点から学ぶシンプル生活の始め方
・家事を減らすコツで1日30分自由時間を作る方法
noteで読むまとめ記事はこちら
ブログ記事「洗濯物をたたまない収納術ズボラでも片付く方法」を、
note向けに流れで読める形に整理しています。
収納の考え方をまとめて振り返りたい方、
あとから見返したい方はこちらもどうぞ。
👉 洗濯物をたたまない収納術 まとめ(noteへ)
最後までご覧いただきありがとうございました。
この記事が参考になれば幸いです。


























































































































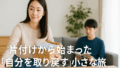
コメント